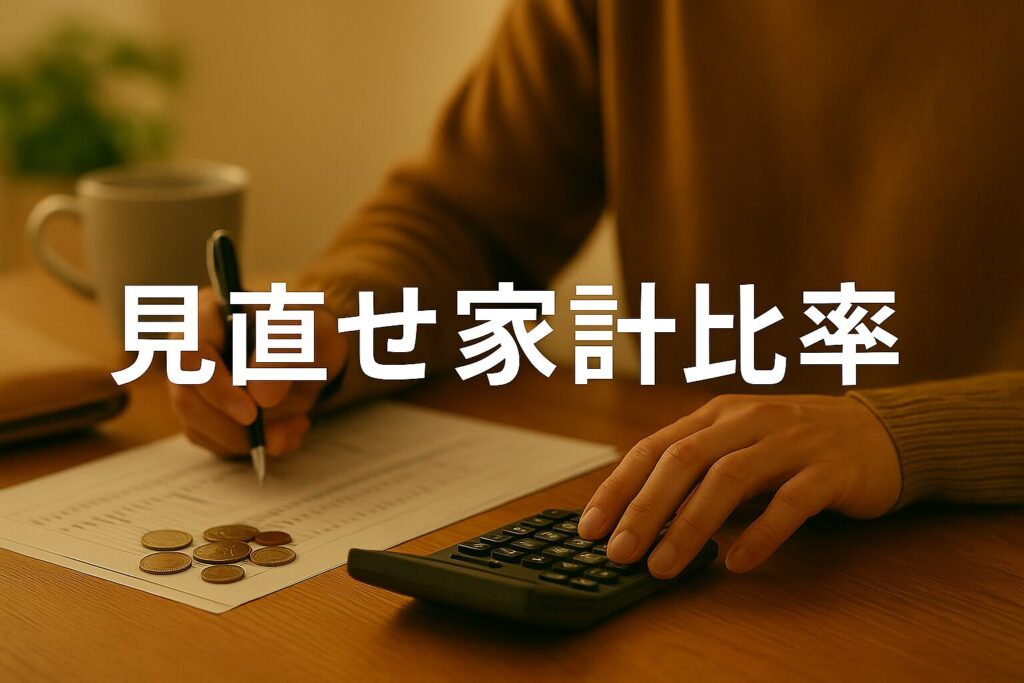
「毎月ちゃんと働いてるのに、なんでお金って貯まらないんだろう…?」
40代も後半にさしかかって、そんなモヤモヤを感じるようになりました。
共働きで収入はそこそこあるし、派手な贅沢をしてるわけでもない。
なのに、資産はなかなか増えないし、FIREなんて全然現実味がない。
投資もやってるのに、なぜか手応えがないんですよね。
これはさすがに何かがおかしいぞ…と思って、家計を見直してみたら、原因は「支出のバランス」でした。
どれも必要そうに見える支出なんだけど、冷静に見ていくとけっこう偏ってる。
通信費が高かったり、保険が手厚すぎたり、レジャー費が地味に響いてたり。
正直、自分でも「これってこんなに使ってたっけ?」って驚くような発見がたくさんありました。
もしかしたら、この記事を読んでいるあなたも、同じようなことを感じていませんか?
「ちゃんとやってるつもりなのにお金が残らない」って、けっこうあるあるですよね。
でも大丈夫。
支出の“金額”じゃなく、“バランス”を整えるだけでも家計ってちゃんと変わります。
この記事では、そんな私のリアルな体験をもとに、40代共働き家庭が見直すべき支出のバランスについて、やさしく解説していきます。
まずは「なぜ支出バランスを整えることが大事なのか」から、一緒に見ていきましょう。
支出バランスを見直す理由
「収入はあるはずなのに、なぜかお金が残らない…」
そんな感覚を持ったこと、ありませんか?
私自身、40代後半になってFIREを意識し始めた頃に、まさにその悩みにぶつかりました。
共働きだし、外食も控えめで、趣味に散財しているわけでもない。
それなのに、なぜか資産が思ったように増えていかない。
積立NISAもやってるのに、投資資金がなかなか作れない。
最初は「収入が少ないからかな」と思っていたんですが、よくよく家計を見直してみたら、支出の“バランス”が崩れていたことが原因でした。
家計の支出って、額そのものももちろん大事なんですが、実は比率(バランス)のほうが家計管理では重要です。
たとえば、固定費が全体の半分を超えていたら、変動費をどれだけ節約しても余力は生まれません。
私のケースでは、特に通信費・保険・教育費が想像以上に重くなっていて、貯蓄や投資にまわす余力をじわじわ圧迫していたんです。
一見「必要経費」に見える部分でも、バランスが崩れていれば、長期的に見ると家計全体をじわじわと苦しめる要因になります。
読者の方にも、「自分ではムダ遣いしてないと思ってるのに、なぜかお金が残らない…」という方は多いのではないでしょうか?
それ、まさに“支出のバランス”が崩れているサインかもしれません。
じゃあ、どうやって家計のバランスを見直せばいいのか?
まずは、支出の現状を正しく把握するところから始めましょう。
次のパートでは、私が実践した「家計の把握ステップ3つ」を紹介します。
家計の把握ステップ3つ

支出バランスを整えるための第一歩は、家計の全体像を「正確に把握すること」です。
私もそうでしたが、「なんとなくこれくらいかな」で管理していると、実際の使いすぎや偏りに気づきにくいんですよね。
そこで私が実際に取り組んで効果を感じた、家計把握の3ステップを紹介します。
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ステップ1 | 家計簿アプリで自動記録 | マネーフォワードMEやZaimなどを使い、銀行・カード・電子マネーを連携。自動で収支を集計してくれるので、続けやすい。 |
| ステップ2 | 支出項目をざっくり分類 | 「固定費」「変動費」「自己投資」「貯蓄・投資」などの大まかなカテゴリに分けて支出比率を見る。 |
| ステップ3 | グラフで見える化する | 可視化すると、偏りがひと目でわかる。例えば食費が20%超えている、通信費が異常に高い…など。 |
私の場合、このステップを踏んでみて、いかに「自分の感覚と実際の家計にズレがあるか」を思い知りました。
とくにサブスク系の固定費や、ちょこちょこ増えていたコンビニ支出など、見直しのヒントがたくさん見えてきました。
ここまでやれば、家計全体のバランスが「数値」として見えるようになり、次に何をすべきかもクリアになります。
次のパートでは、そこから見えてきた理想的な支出バランスのパターンについて紹介します。
理想的な支出割合3パターン
支出を見える化したら、次に知っておきたいのが「理想的な支出の割合」。
いわゆる“家計の黄金比”と呼ばれるものです。
もちろん家庭によって違いはありますが、目安があるだけでも「何が多すぎるのか」「何を削れそうか」が判断しやすくなります。
ここでは、私が実際に参考にした、代表的な3つの支出割合パターンをご紹介します。
| パターン | 特徴 | 支出の目安比率(例) |
|---|---|---|
| 標準型 | 一般的な家庭に多いバランス | 住居20%、食費15%、通信費5%、保険5%、光熱費6%、教育費10%、貯蓄・投資10〜15% |
| FIRE型 | 貯蓄・投資を優先する設計 | 住居15%、食費12%、通信費3%、保険3%、教育費5%、貯蓄・投資30%以上 |
| ゆるFIRE型 | 現実的かつ持続可能 | 住居18%、食費13%、通信費4%、保険5%、教育費8%、貯蓄・投資20%前後 |
私は、最初は「標準型」に近い支出構成でしたが、FIREを意識するようになってから「ゆるFIRE型」に寄せていきました。
とくに意識したのは、「固定費をできるだけ圧縮すること」と「貯蓄・投資の比率を先に決めて、残りで生活する」感覚を持つこと。
この比率を基準にして考えるようになってから、支出に対する感覚が大きく変わりました。
たとえば、「食費が増えてもその分他を削ればOK」といった柔軟な調整ができるようになったり、支出の全体感がつかめるようになったりします。
あくまで目安なので、すべてをこの通りにする必要はありません。
でも、理想のバランスが見えているだけで、日々の判断がしやすくなるのは間違いありません。
次のパートでは、こうして見えてきた「崩れた家計の立て直し方」について、私が実践した3つの方法をお伝えします。
崩れた家計を整える3つの方法

理想の支出バランスがわかっても、いざ家計を見直すと「全然バランスが取れていない…」と感じる方も多いはず。
私もまさにその状態でした。「どこから手をつければいいかわからない」という迷いに直面していました。
でも安心してください。家計のバランスは、完璧を目指さず、少しずつ整えていけば十分に改善できます。
ここでは、私自身が実践して効果を感じた「崩れた家計を整えるための3つの方法」を紹介します。
| 方法 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 固定費を見直す | 家賃・通信費・保険など、毎月決まった支出を優先的に見直す。 | 一度見直すだけで長期的な節約効果が期待できる。 |
| 2. 支出に優先順位をつける | 「必要」「あると便利」「不要」に分類。 | 家族で共有すればムダ遣いの抑止にもなる。 |
| 3. 先取り貯蓄・投資を導入 | 給与から先に投資・貯蓄額を確保。 | 「残ったお金で生活する」スタイルが継続のコツ。 |
特に「先取り貯蓄・投資」は、FIREを目指す家庭には欠かせない習慣です。
私もこの考え方を取り入れてから、安定して投資に回せるお金が確保できるようになりました。
最初は一つずつでも構いません。小さな改善の積み重ねが、大きな変化につながります。
家計の黄金比を保つために
せっかく整えた支出バランスも、継続できなければ元に戻ってしまいます。
実際、私もサブスクや外食のリバウンドを経験しました。
そこで、支出の黄金比を保つために日々行っている習慣を紹介します。
1. 月1回の家計チェックを習慣にする
月末や給料日前に、家族で10分でも支出を振り返る時間を設けると意識がリセットされます。
家計簿アプリを使えば集計も手間なし。
2. 支出が増えたら即チェック
「最近ちょっと出費が多いな」と思ったら、そのタイミングで見直します。
私は子どもの習い事費が増えたとき、外食やレジャー費を調整して対応しました。
3. 年に1〜2回は家計の“棚卸し”を実施
サブスク、保険、スマホプラン、クレカなどをまとめて見直す時間をつくるだけで、支出の最適化がグッと進みます。
こうした小さな仕組みを生活に組み込むことで、無理なく支出のバランスが保てるようになります。
FIREを目指す家庭にとって、支出管理は最も大切な“守り”の戦略です。
まずはできるところから、支出の見直しをスタートしてみましょう。