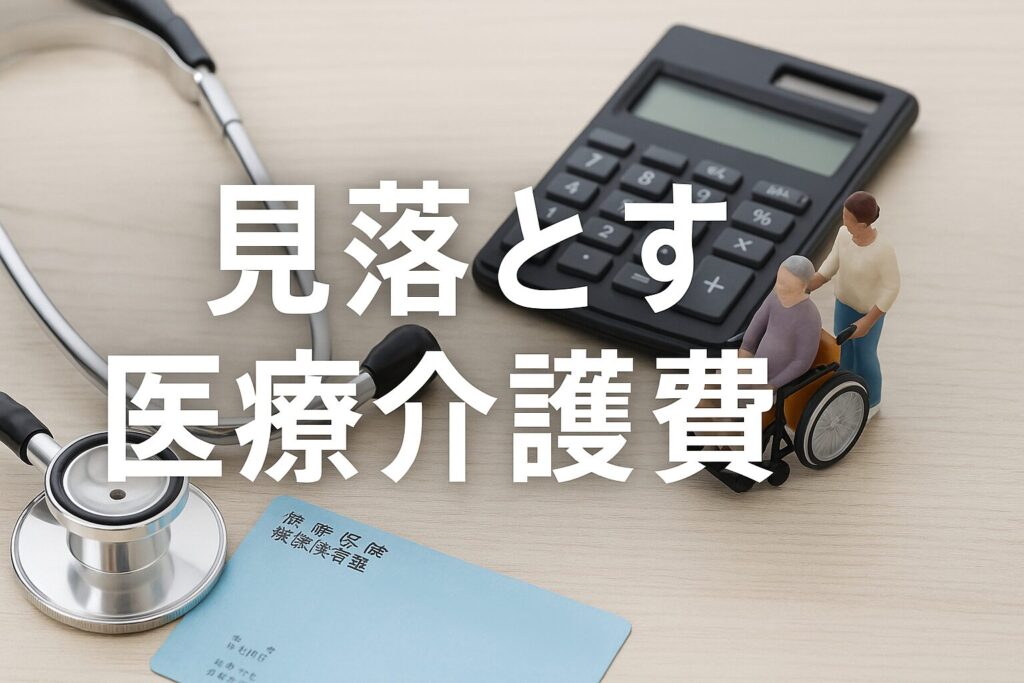
FIREを目指していると、どうしても資産運用や節約といった「攻めの部分」に目がいきがちです。
しかし意外と見落とされやすいのが、老後に確実に増えていく医療費や介護費のリスクです。
今は健康で大きな医療費を経験していなくても、年齢を重ねるにつれて通院や薬代、検査費用などがじわじわと家計を圧迫していきます。
さらに将来、介護が必要になった時の費用は想像以上に高額になるケースもあり、「想定外の出費」でFIRE計画そのものが揺らぐ人も少なくありません。
私自身も、現時点では医療費に大きな負担を感じたことはありません会社で安く加入できる掛け捨ての医療保険に入ってはいるものの、これが本当に必要なのか、それとも貯蓄で備えるべきなのかを見直すタイミングに来ていると感じています。
特に不安なのは、やはり介護費用です。
いざ必要になったとき、「どのくらい準備しておけば安心なのか」が見えにくいため、将来の生活設計に不安が残ります。
だからこそ、FIREを計画するうえで「医療・介護リスクをどう組み込むか」は避けて通れない課題です。
医療制度や高額療養費制度の仕組みを正しく理解しつつ、保険と貯蓄のバランスを考え、家族で共有しておくことが、安心したFIRE生活を送るためのカギになります。
本記事では、FIRE準備で見落とされがちな医療・介護費リスクについて、制度の限界やリアルな費用感、備え方のポイントをわかりやすく解説していきます。
「今は大丈夫」と思っている人ほど、ぜひ最後まで読んで参考にしてみてください。
老後資金に潜む医療費の見落としポイント
FIREを目指す上で、資産計画を立てる人の多くは「生活費」と「投資収益」に注目しがちです。
しかし、実際の老後生活でじわじわ効いてくるのが医療費です。
現役時代は健康保険に守られている安心感もあり、大きな病気をしない限り「そんなにかからないだろう」と考えがちですが、老後は事情が変わってきます。
まず押さえておきたいのは、年齢を重ねるほど通院回数や薬代が増えるという現実です。
厚生労働省の統計では、医療費の自己負担額は70代から急激に増える傾向があります。
特に生活習慣病(高血圧・糖尿病・脂質異常症など)は一度診断されると長期的な通院や投薬が必要になり、毎月数千円〜数万円が固定費化してしまいます。
これは一度始まるとなかなか減らせない支出であり、FIRE後の「想定外の固定費」として家計を圧迫するリスクがあります。
さらに、検査や入院の費用も忘れてはいけません。
入院すると食事代や差額ベッド代などが意外と大きな負担になります。
高額療養費制度があるとはいえ、自己負担はゼロにはなりませんし、先進医療や自由診療を選んだ場合は全額自己負担になります。
「想定外の医療費で貯蓄が一気に減った」という話は珍しくありません。
私自身もまだ大きな医療費負担を経験していませんが、逆にそれが「見落とし」につながりやすいと感じています。
健康であるうちはリスクを軽く見てしまいがちですが、老後の医療費は静かに家計をむしばむコストです。
では、どう備えるべきでしょうか。
一つの考え方は、「毎月の生活費に医療費枠をあらかじめ組み込む」ことです。
例えば月2万円を医療費予備費として計上すれば、通院や薬代に対応しやすくなります。
また、保険についても「必要最小限」で良いのか、それとも入院保障などを確保しておくべきかを定期的に見直すのが大切です。
FIRE後は会社の団体保険を利用できなくなるケースも多いため、今のうちにシミュレーションしておくと安心です。
ポイントは「まだ健康だから大丈夫」と思わないこと。
むしろ健康なうちにこそ、老後の医療費を現実的に想定し、資金計画に組み込んでおくことがFIRE成功のカギになります。
高額療養費制度の仕組みと限界を知る

医療費の備えを考えるとき、多くの人が「高額療養費制度があるから大丈夫」と安心します。
確かにこの制度は、病気やケガで医療費が高額になった際に自己負担を一定額まで抑えてくれる、とても心強い仕組みです。
しかし、「万能」ではないという点を理解していないと、FIRE後の資金計画に落とし穴が生まれます。
まず、仕組みを簡単に整理しておきましょう。
高額療養費制度では、同じ月にかかった医療費(保険適用分)が自己負担限度額を超えた場合、その超過分が払い戻されます。
限度額は年齢や所得水準によって決まっており、現役並み所得の人であれば1カ月の自己負担はだいたい8万円〜9万円程度に収まるケースが多いです。
つまり「数百万円かかったとしても、最終的には数万円で済む」ことがあるわけです。
一見すると非常に安心できる制度ですが、実際にはカバーされない費用が数多く存在します。
例えば、以下のような費用は自己負担になります。
特に差額ベッド代は1日数千円〜数万円と病院によって大きく異なり、数週間の入院で数十万円の負担になることも珍しくありません。
「制度で守られているから安心」と思っていても、こうした自己負担部分が実際には大きな家計ダメージとなるのです。
さらに注意したいのは、払い戻しがすぐに受けられるわけではないという点です。
実際には一度窓口で医療費を全額支払ったあとに申請を行い、後日差額が戻ってきます。
最近は「限度額適用認定証」を事前に取得していれば窓口での支払いを抑えられますが、制度を正しく理解し、手続きの準備をしていないと一時的に大きな出費が必要になるケースもあります。
私自身も、この制度があることは知っていても、「差額ベッド代や食費は対象外」という点を深く意識していませんでした。
会社の医療保険に加入している今はまだ安心感がありますが、FIRE後には自分で備える必要があります。
つまり、FIREを計画するなら「高額療養費制度で守られる部分」と「守られない部分」を切り分けて考えることが大切です。
制度を過信せず、自己負担となる可能性のある費用を現実的に積み上げていくことで、より確実な資金計画が立てられます。
長期的に増える介護費のリアルな負担
FIREを計画するうえで、医療費と並んで大きな不安要素となるのが介護費用です。
医療費はある程度統計や制度から見積もりやすいのに対し、介護は「いつ始まるか」「どれくらい続くか」が読めないため、資金計画の中でも特に扱いが難しい支出です。
まず押さえておきたいのは、介護は短期で終わらないケースが多いという現実です。
厚生労働省の調査によると、要介護状態が続く平均期間は男性で約9年、女性では約12年とされています。
つまり、一度介護が始まれば10年前後にわたって費用が発生する可能性が高いのです。
しかも介護の度合いによって必要な金額が大きく変わるため、想定の幅が非常に広いのが特徴です。
公的介護保険を利用すれば一部の費用はカバーされますが、それでも自己負担は軽くありません。
例えば在宅介護の場合、自己負担は月5〜10万円程度になることが多いです。
施設介護に移ると、さらに費用は跳ね上がり、特別養護老人ホームなら月10〜15万円、民間の有料老人ホームや介護付き施設では月20〜30万円以上かかるケースもあります。
これが数年〜10年以上続くと考えると、介護費用だけで数百万円から場合によっては1,000万円を超えることも珍しくありません。
私自身も「将来介護が必要になったら、どれくらい準備しておけば安心なのか」が見えにくいことに不安を感じています。
医療費と違って定期的に請求される**“介護の固定費化”**は、FIRE後の家計にとって大きなリスクです。
特にFIRE生活では収入が年金や資産運用益に限られるため、想定以上の介護費がかかると「資産の取り崩しスピードが加速する」リスクに直結します。
では、どう備えれば良いのでしょうか。
一つの考え方は、「介護リスク用の専用資金を分けておく」ことです。
例えば、老後資金全体の中から300〜500万円程度を「介護用」として切り分けておくと、心理的な安心感につながります。
また、公的介護保険のサービス範囲を理解しておき、在宅介護・施設介護それぞれの費用シミュレーションを事前にしておくと、家族での意思決定もスムーズになります。
重要なのは、「介護はいつか必ず訪れるもの」として計画に組み込む姿勢です。
今は健康で実感がなくても、将来の長期的な負担を資金計画に盛り込むことが、FIREの持続可能性を高める第一歩となります。
医療・介護リスクに備える資金の考え方

FIREを目指すうえで、最も頭を悩ませるのが「どれくらい医療・介護費を見込んでおけば安心なのか」という点です。
生活費や趣味の支出はある程度コントロールできますが、医療や介護は予測不能かつコントロールが難しい支出だからです。
まず意識すべきなのは、医療費と介護費は性質が違うということです。
医療費は一時的に大きくかかることがあっても、高額療養費制度などで自己負担はある程度抑えられます。
一方で介護費は「長期にわたって継続的に発生する」ため、積み重ねが大きな負担になるのです。
この違いを踏まえて、それぞれにどう資金を割り当てるかを考える必要があります。
一つの目安として、老後の医療費は平均で約1,000万円程度かかるといわれています。
ただし、この数字は人生全体の平均値であり、実際には個人差が大きいものです。
そのため、「生活費に加えて年間数十万円程度を医療費予備費として確保する」くらいの柔軟な想定が現実的でしょう。
一方で介護費については、前章で触れたように数百万円〜1,000万円超の可能性があります。
そこで有効なのが、医療・介護費専用の資金枠をあらかじめ分けておくことです。
例えば、FIRE資金のうち生活費とは別に「介護・医療リスク用」として500万円程度をプールしておくと、想定外の出費にも冷静に対応できます。
この資金はできれば流動性の高い現金や安全資産で確保するのが安心です。
私自身も「医療保険は会社の団体契約で最低限加入している」状態ですが、FIRE後にはその選択肢がなくなるため、貯蓄で備える部分を増やすべきだと感じています。
特に介護については将来の負担感が読めないため、専用資金を確保することで不安がやわらぐと思っています。
また、資産全体のバランスも重要です。
運用益だけで医療・介護費をまかなうのはリスクが高いため、現金比率を一定程度維持しておくことがポイントです。
インフレや長寿リスクを考慮しながらも、「いざというときにすぐ使える資金」を残しておくことで、安心感が格段に違ってきます。
つまり、医療・介護リスクへの備えは「特別な追加支出」として後回しにするのではなく、FIRE計画の初期段階から組み込むべき固定項目です。
その意識を持つだけでも、将来の不安は大きく軽減されます。
保険と貯蓄のバランスをどう取るか
医療や介護リスクに備える方法として、よく議論になるのが「保険で備えるか、それとも貯蓄で備えるか」という問題です。
どちらもメリットとデメリットがあり、FIREを目指す人にとっては特にバランスの取り方が重要になります。
まず保険について考えてみましょう。
医療保険や介護保険に加入していれば、大きな出費が発生した際に自己負担を軽減できます。
例えば入院給付金や手術給付金があれば、医療費の急な負担をある程度吸収できます。
また、民間の介護保険では、要介護認定を受けた際に一時金や年金形式で給付を受けられる商品もあります。
突発的なリスクに対する安心感を得られるのは、保険の大きなメリットといえるでしょう。
しかし、FIREを考えるうえでは「保険料」という固定支出が大きなデメリットになります。
掛け捨て型であれば長期的に見て払い損になる可能性がありますし、貯蓄型や終身型では資産運用効率が落ちてしまうリスクがあります。
特にFIRE後は収入源が限られるため、毎月の保険料が家計に重くのしかかることは避けたいものです。
一方で、貯蓄で備える場合は自由度が高いのが強みです。
使い道を医療・介護費に限定せず、他の目的にも流用できるため、資金を有効に使えます。
また、必要なときに必要な分だけ使えるので「払い損」がありません。
ただし、突発的に大きな費用が発生したとき、十分な資金が確保できていなければFIRE計画自体が崩れるリスクもあります。
私自身も会社の団体医療保険に最低限加入していますが、今後FIREを考えるなら「保険を縮小して、その分を貯蓄に回す」方向で検討しています。
医療費については高額療養費制度で一定の上限があるため、貯蓄で対応できる部分は多いはずです。
ただし、介護については長期戦になる可能性が高いため、介護保険を部分的に活用するか、専用の貯蓄枠を作っておくのが安心だと感じています。
結論としては、「医療は貯蓄中心+最低限の保険」「介護は専用資金+必要に応じて保険」という組み合わせが現実的でしょう。
過度に保険に頼らず、かといって完全に貯蓄一本でも不安が残るため、両者のバランスを取りながら、自分と家族の状況に合ったプランを作ることが大切です。
家族で共有すべき医療・介護の備え

医療や介護のリスクは、本人だけの問題ではありません。
むしろ実際に負担を背負うのは、配偶者や子どもなど「家族全体」であることが多いのです。
だからこそ、FIREを目指す家庭では「お金の備え」と同じくらい「情報共有」が大切になります。
まず医療費については、どんな保険に入っているのか、自己負担が発生した場合はどう対応するのかを家族で話し合っておくべきです。
例えば「高額療養費制度を利用するにはどんな手続きが必要か」「限度額適用認定証はどうやって取得するのか」など、知っているか知らないかで負担感は大きく変わります。
本人が入院して動けない状況になれば、代わりに家族が動くことになります。
準備や手続きを家族で共有しておけば、不安や混乱を最小限に抑えられるのです。
介護についても同じです。
誰かが要介護状態になった場合、「在宅で介護するのか」「施設を利用するのか」という選択が家族に突きつけられます。
費用面だけでなく、介護にかかわる家族の時間的・精神的負担も大きな要素です。
その場になって初めて話し合うのでは遅く、前もって「どこまで在宅で頑張るのか」「施設利用に切り替える基準は何か」を共有しておくことが、家族全体の安心感につながります。
私自身も、将来介護費用がどれくらい必要になるかを想像すると不安を感じます。
だからこそ「家族で一緒に考える」ことが大事だと思っています。
FIREは単なるお金の計画ではなく、家族と一緒に歩むライフプランです。
お金の備えを整えるだけでなく、「もしもの時にどう対応するか」を家族会議で共有しておけば、突然の事態にも落ち着いて行動できるでしょう。
具体的には、以下のような点をメモやノートにまとめ、家族で共有するのがおすすめです。
- 加入している医療保険・介護保険の内容
- 高額療養費制度の申請方法や書類の所在
- 医療費・介護費用に充てられる貯蓄口座
- 在宅介護か施設利用かの希望
- 緊急時の連絡先や相談窓口
これらを整理しておくだけでも、家族全員が「安心のセーフティネット」を持てるようになります。
FIREはゴールではなく、家族で築く新しい生活のスタートライン。
そのためにも、医療・介護リスクを「自分ごと」から「家族ごと」に切り替えて準備することが欠かせません。
まとめ|医療・介護費リスクを踏まえたFIRE計画
FIREを目指すとき、多くの人が注目するのは「生活費をいかに抑えるか」「どんな投資で資産を増やすか」といった部分です。
もちろんそれも大切ですが、忘れてはいけないのが**医療費と介護費という“見えにくいリスク”**です。
これまで見てきたように、医療費は年齢を重ねるほどじわじわと増え、生活費に固定的に組み込まれていきます。
さらに介護費は、数年から10年以上続く可能性があり、数百万円〜1,000万円規模にふくらむこともあります。
これらを軽視したままFIREを始めてしまうと、数年後に「想定外の出費で資産が急減」という状況に陥りかねません。
大切なのは、制度の仕組みを理解し、限界を知ったうえで備えることです。
高額療養費制度は確かに心強いですが、差額ベッド代や食費、先進医療は対象外です。
介護も公的保険で一部はカバーされるものの、施設費や在宅介護の人件費までは十分にまかなえません。
制度を過信せず、「どの部分が自己負担になるのか」を明確にしておくことが、FIRE計画を崩さないための第一歩です。
備え方のポイントは3つあります。
私自身もまだ大きな医療費の経験はありませんが、介護費用に関しては特に不安を感じています。
だからこそ、資産運用の成果だけに頼るのではなく、「リスクを見える化」して家族と共有しておくことが大切だと実感しています。
FIREはゴールではなく、新しい生活のスタートライン。
その生活を安心して続けるためには、医療・介護リスクをしっかり組み込んだ資金計画が欠かせません。