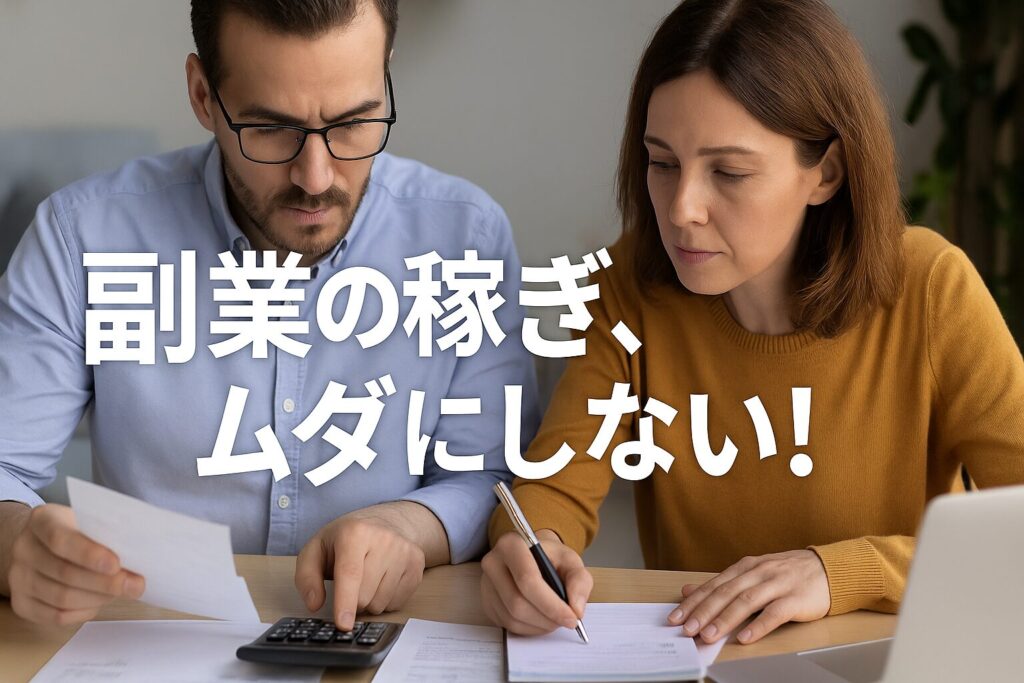
「40代から副業を始めたけど、手元に残るお金が全然増えない…」
これ、正直に言うと、私自身がずっと感じてきた悩みです。
私も、せどりに1年ほどチャレンジしましたが、利益はほぼゼロ。
むしろ、「これ、本当に意味あるの?」と途中で何度も疑問に思ったほどです。
投資もやっていますが、そちらは自動で税金が引かれるので、手間はかかりませんでした。
でも、副業となると、「税金対策ってどうすればいいんだろう?」と迷う人がほとんどだと思います。
せっかく頑張って稼いでも、税金でごっそり持っていかれる。
これじゃ、副業を続けるモチベーションも下がりますよね。
私のまわりでも、「確定申告って必要なの?」「経費ってどこまで認められる?」という声が多いです。
本業・家計・副業のバランスも悩みどころです。
私も「本業に支障が出るくらいなら副業は控えた方がいい」と常に意識しています。
この記事では、「40代共働きが実践できる、手取りを最大化する税金対策」について、私自身の経験も交えつつ、わかりやすく解説していきます。
専門用語はできるだけ避けて、初心者でも実践できるノウハウをまとめました。
同じ悩みを持つあなたに、「あ、これならできそう」と思ってもらえるような内容です。
副業の収入と税金の基本から、確定申告・控除・経費の考え方、実際に家計にプラスを残すコツまで、無駄なく、シンプルに伝えます。
「副業やってるけど、結局手元に残るお金が少ない…」
そんな悩みを一緒に解決しましょう。
副業の収入と税金の基本を知ろう
「副業で少しでも家計の足しにしたい」と考える共働き世代は多いと思います。
でも、いざ副業を始めてみると「稼いだ分だけ手元に残るわけじゃない」という現実に直面します。
これは、副業の収入には必ず“税金”がかかってくるからです。
私もせどりを1年やってみて、「売上=利益」ではないことを痛感しました。
仕入れや送料、そして“税金”まで考えると、実際に残るお金は思ったより少なかったんです。
「副業の収入って、いくらから税金がかかるの?」「副業分はどうやって申告するの?」
こうした疑問を持つ人は多いでしょう。
まず、大前提として副業で得たお金は“雑所得”や“事業所得”という扱いになり、一定額を超えると税金の対象になります。
これ、バイトのように“源泉徴収”で自動的に引かれるわけではありません。
特に本業で会社員をしている場合、副業の収入は本業の給与と合算して税額が決まるため、「副業分だけ別に税金を払う」とは限りません。
たとえば、こんなイメージです。
| 収入の種類 | 会社で処理 | 自分で処理 | 税金のポイント |
|---|---|---|---|
| 本業(会社員) | あり | なし | 給与天引き(年末調整) |
| 副業(自営業・せどり等) | なし | あり | 原則として自分で申告&納税 |
「副業だからバレない」「確定申告は必要ない」…そんな甘い考えでいると、後で痛い目を見ます。
特に40代になると、「住宅ローン」や「子育て費用」など、今まで以上に家計管理がシビアになります。
副業で得たお金をしっかり手元に残すには、「どこから税金がかかるのか」「どうやって納税するのか」を最低限知っておくべきです。
私自身、「思ったより残らないな…」と感じてから、ようやく税金の仕組みを勉強しました。
最初は正直、面倒くさいし難しそうだなと思っていましたが、“最低限のポイント”だけ押さえれば大丈夫です。
このあと、「確定申告が必要になるケース」「控除の活用法」「経費にできるもの」など、具体的なポイントをひとつずつ解説していきます。
「税金のことは後回し」だと損します。
今から一緒に、知っておくべきポイントを押さえていきましょう。
確定申告が必要になるケースとは

副業を始めると、「本当に自分に確定申告が必要なのか?」と気になる人は多いと思います。
正直、私も最初は「そんなに稼いでいないし、申告しなくていいよね?」と甘く見ていました。
でも、この認識はかなり危険です。
まず、副業の収入が年間20万円を超える場合、原則として確定申告が必要です。
この「20万円ルール」は、会社員が本業の給与とは別に得た所得に適用されます。
たとえば、せどりやブログ収入、ライター業など、自分で稼いだ副業の合計が20万円を超えたらアウト。
「利益が少ないから大丈夫」ではなく、「経費を引いた後の純利益が20万円を超えたら」確定申告の義務が発生します。
逆に、年間20万円以下なら申告不要と言われることも多いですが、注意が必要です。
なぜなら、住民税は申告しないといけないケースがあるからです。
たとえば、たとえ所得税の確定申告が不要でも、自治体への住民税申告は必須になることもあります。
「なんでこんなに細かいの?」と思いますよね。
正直、私も副業を始めたばかりの頃、こうしたルールを知らずに後から調べて焦った経験があります。
確定申告なんて自分には無関係だと思っていたけど、税務署から通知が来たら一気に青ざめるはずです。
また、副業の種類によっても申告義務の内容が変わります。
たとえば、アルバイトやパートで副業をしている場合は、会社側で源泉徴収されていることが多いですが、それ以外の個人でやる副業(せどり・ブログ・クラウドワークス等)は、自分でしっかり申告する必要があるんです。
「まだ大丈夫だろう」と油断しがちな副業の申告ですが、後回しにしてしまうと、あとで手続きが面倒になるだけでなく、場合によっては追徴課税なんてこともあり得ます。
ここで一度、確定申告が必要になる代表的なパターンを表にまとめます。
| 副業の種類 | 年間利益20万円以下 | 年間利益20万円超 | 住民税申告 |
|---|---|---|---|
| せどり・ブログ | 原則不要 | 必要 | 場合によって必要 |
| パート・バイト | 基本的に会社処理 | 必要 | 原則必要 |
つまり、「自分は関係ない」と思わずに、一度自分の副業収入をしっかり見直すことが大切です。
私のように、「まだそこまで稼げていないから…」と油断するのではなく、今のうちから正しい知識を持っておくことで、余計なトラブルを防げます。
「いつから、どんな場合に申告が必要なのか」、自分の副業状況を毎年しっかり確認しましょう。
控除を使って税負担を減らすコツ
「副業で稼いでも、結局税金で持っていかれるだけじゃ意味がない」
正直、そう思っている人は多いはずです。
私自身もせどりを始めてみて、利益が少ない中でも「できるだけ手取りを増やすには?」と頭を悩ませてきました。
そんなとき知っておきたいのが“控除”の仕組みです。
控除とは、課税対象となる所得から一定額を差し引くことができる制度のこと。
要するに、「税金がかかる前に“引いてもらえる枠”」と考えてください。
たとえば、副業で使える主な控除は以下の通りです。
| 控除の種類 | 内容・ポイント |
|---|---|
| 基礎控除 | 誰でも受けられる。48万円(令和2年以降) |
| 社会保険料控除 | 国民年金や健康保険など、支払った分を全額控除 |
| 生命保険料控除 | 生命保険に入っていれば一定額まで控除 |
| 医療費控除 | 1年間で10万円以上の医療費があれば超過分が控除 |
| 寄付金控除 | ふるさと納税などが該当 |
この中でも、「基礎控除」は全員に自動で適用されるので、難しく考えなくて大丈夫です。
でも、「社会保険料」や「生命保険料」「医療費」などは自分で申告しないと控除されないので、うっかり忘れると損です。
副業で使える控除は、「確定申告」のときに申請するものが多いです。
例えば、もし副業の年間利益が48万円だった場合、基礎控除で全額控除されるので、課税対象はゼロになります。
逆に、せっかく控除できるのに「面倒だから…」と放置していると、本来払わなくてよかった税金まで取られてしまうことに。
ここで「どれだけ控除を使えば手元に残るお金が増えるか」ざっくりイメージしてみましょう。
例:副業利益が50万円の場合(会社員・独身)
- 副業利益:50万円
- 基礎控除:48万円
- 課税対象:2万円(50万-48万)
この場合、実際に税金がかかるのは2万円分だけです。
控除を活用しない手はありません。
特に共働きや子育て世帯は、「医療費控除」「生命保険料控除」も積極的に使えるケースが多いです。
私も、子どもの医療費や自分の保険料は毎年見直して、「これは控除できるかな?」と確認するのが習慣になりました。
「控除ってなんだか難しそう…」と思いがちですが、一度仕組みを知ってしまえば手続き自体はシンプルです。
申告時に漏れなく控除申請して、ムダな税金は1円たりとも払わないようにしましょう。
経費にできるもの・できないもの
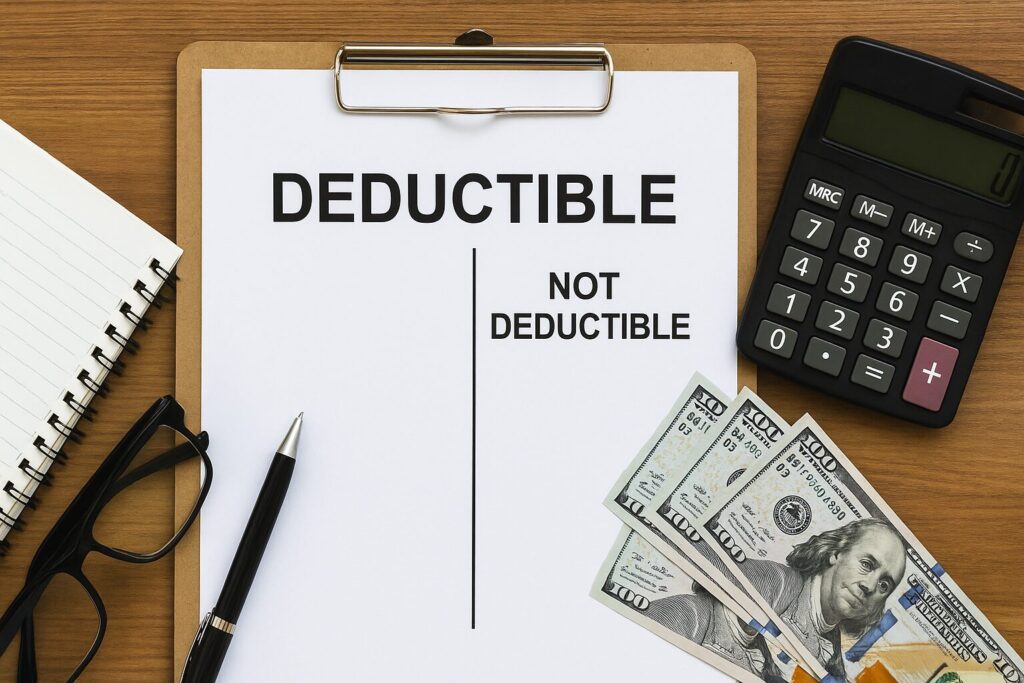
副業を始めたばかりの人にとって、「どこまでが“経費”として認められるの?」という疑問はかなり大きいと思います。
私自身、せどりをやっていたとき「これは経費にしていいの?」「ここまで申告したら怪しまれる?」と不安になり、いろいろ調べたり、詳しい人に聞いたりしました。
まず大前提ですが、経費とは「副業のために実際に使ったお金」のことです。
「これがなければ副業が成り立たなかった」と説明できるものだけが、経費として認められます。
一方で、“プライベートの出費”は経費になりません。
ここが最大のポイントです。
では、具体的に何が経費になるのか?
分かりやすく表でまとめます。
| 経費になるもの | 経費にならないもの |
|---|---|
| 仕入れ代・商品の送料(せどり) | 家族の食費や日用品の購入 |
| 副業用のパソコン・スマホ | 個人的な趣味で使ったガジェット |
| 副業のための書籍・勉強会参加費 | 家族旅行やプライベートの外出費用 |
| 事務所や作業スペースのレンタル費 | 自宅の家賃や光熱費(※全額はNG。按分が必要) |
| ネットショップ運営費・広告費など | 趣味で作ったブログの運営費(収益なしなら基本NG) |
せどりの場合は「仕入れにかかった全ての費用」が経費になるのが一番わかりやすい例です。
商品を発送するための送料や、梱包資材代ももちろんOK。
また、副業用にパソコンやスマホを買った場合も、その用途が副業中心なら経費で計上できます。
逆に、「どう考えても仕事と関係ないもの」は絶対に経費にできません。
たとえば、「子どもの運動会のためのカメラ」は家族用なのでアウト。
「家賃や光熱費」も、もし自宅を作業場にしているなら、副業で使った分だけを“按分”して経費にできるというルールです。
(例:自宅の部屋の2割を副業スペースにしているなら、家賃の2割だけ経費にできる)
私も最初は「どこまで経費で落とせるか」で悩みましたが、迷ったら「本当に副業のため?」と自問自答するのが鉄則です。
そして、必ずレシートや領収書は取っておくこと。
これがないと、いざというとき認められません。
注意点として、「なんでも経費にしすぎる」と税務署から指摘されるリスクもあるので、「これなら堂々と説明できる」という出費だけを経費として申告しましょう。
副業を続けていく上で、経費の感覚を早めにつかんでおくことは手取り最大化への第一歩です。
「どこまでOK?」「どこからNG?」を毎回迷わないためにも、普段から記録をつけておくのがおすすめです。
副業の税金で損しないための注意点
副業で得たお金を「ちゃんと申告したつもりだったのに、思ったより手元に残らなかった」
あるいは、「あとから税金が追加でかかった」
こういう声は、私の周りでも本当に多いです。
特に40代の共働き世代は、本業と家計で頭がいっぱい。
副業の税金対策まで手が回らず、“気付かぬ損”をしている人も少なくありません。
まず押さえておきたいのは、副業で得た利益は“住民税”にも反映されるという点です。
「所得税だけ申告すればいい」と思いがちですが、実際には自治体への住民税申告も重要です。
申告しないと後で自治体から通知が来ることもあり、下手をすると本業の会社に副業がバレる原因になるケースも。
さらに、副業の申告で“税金を多く払ってしまう”落とし穴もあります。
たとえば、「経費をきちんと計上しない」「控除を申告し忘れる」と、本来よりも多く税金を支払うことに。
私自身、最初は面倒くさがって細かい経費を省略してしまい、「こんなに税金取られるなら副業の意味がないじゃん!」と後悔したことがあります。
また、副業の利益が増えてくると、税率そのものが上がる(累進課税)ことも頭に入れておきたいポイント。
「本業の給与と合算して税金計算される」ので、本業が高収入だと、副業分の税率も思ったより高くなることがあるんです。
ここで、「副業で損しがちなパターン」をまとめます。
| 損しやすいパターン | 注意点・解決策 |
|---|---|
| 経費や控除の申告漏れ | 毎月記録&レシート保管で徹底防止 |
| 住民税申告の失念 | 副業分の住民税は必ず自治体にも申告する |
| 副業が会社にバレてしまう | 住民税を「自分で納付」に指定する |
| 利益増で税率アップを想定していない | 収入が増えたら、翌年の税金も意識する |
特に気をつけたいのが「住民税の普通徴収」です。
副業の収入がある場合、「住民税の納付方法」を“自分で納付(普通徴収)”に指定すれば、会社にバレにくくなります。
申告時のチェックボックスひとつで防げるので、副業バレが気になる人は必ず確認しましょう。
最後に、「税金を払う=損」と思わず、正しく申告することでトラブルを防ぐことも大切です。
「どうせバレないだろう」「少額だから大丈夫」と安易に考えず、最初からルールを守って副業を続けることが、結局は一番お得だと私は思います。
家計と副業収入の賢い管理方法
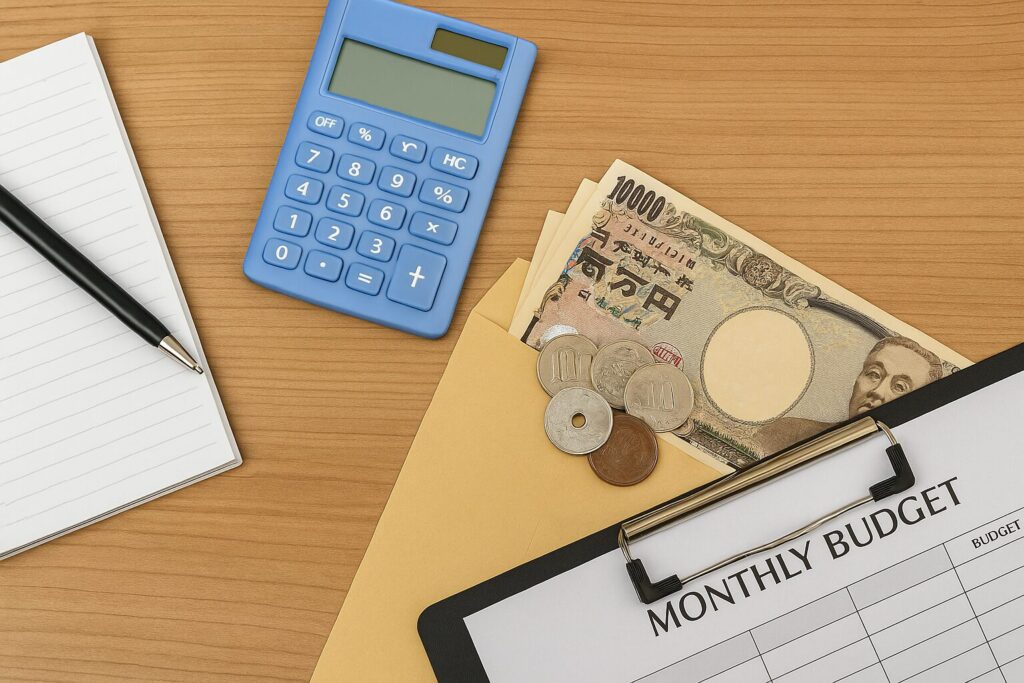
副業でせっかく稼いだお金、「気づいたら全部消えていた…」という経験、正直ありませんか?
私も最初は「副業で入ったお金=自由に使っていいお小遣い」感覚でいたので、気がつくと何に使ったかすら分からないことがよくありました。
でも本当に手取りを最大化したいなら、「家計と副業収入の分け方」と「管理方法」がカギです。
まずおすすめなのが、副業専用の銀行口座を作ること。
副業収入と本業の給与、支出がごちゃ混ぜだと、お金の流れが見えなくなります。
私も副業用の口座を分けてから、「何をどれだけ使ったか」「いくら利益が残ったか」が圧倒的に見やすくなりました。
また、副業の支出・経費を日々記録する習慣も重要です。
最近は、スマホの家計簿アプリやエクセルでカンタンに記録できるので、「レシートをもらったらすぐ記録」を意識してみてください。
経費計上の漏れもなくなり、確定申告時のストレスも激減します。
下の表のようにシンプルな項目だけでも十分です。
| 日付 | 入金(売上) | 出金(経費) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 6/1 | 10,000円 | 1,000円 | 梱包資材代 |
| 6/5 | 8,000円 | 0円 | ― |
こうやって記録を積み重ねるだけで、「自分の副業が儲かっているのか」「どこでムダ遣いしているのか」がよく見えてきます。
さらに、副業の使い道ルールを決めるのもおすすめです。
たとえば「副業収入は教育費や将来の貯金に回す」「絶対に生活費には手を付けない」など、目的を決めておけば浪費しにくくなります。
私は「副業分は家族のための特別出費や将来の投資に充てる」と決めています。
注意したいのは、本業の仕事や家庭生活を犠牲にしてまで副業に時間やエネルギーを使わないこと。
「無理をして副業にのめり込むと、結局どちらもうまくいかない」
私自身、本業がおろそかにならないよう、いつも優先順位を意識しています。
最後に、家計全体で「お金の流れを見える化」することが、副業の手取りを最大化するためのベースになります。
特に共働きや子育て世代は支出も多いですが、副業収入を上手に管理してこそ「お金が貯まる仕組み」が作れます。
まとめ|40代共働きのための副業税金対策
ここまで「40代共働きが実践!副業で手取りを最大化する税金対策のコツ」と題して、副業と税金の基本から、申告・控除・経費・家計管理まで、順を追ってお伝えしてきました。
最後に、要点とこれから副業を続けるうえでのアドバイスをまとめます。
まず、副業を始めたら「収入と税金の仕組み」を正しく知ることが大前提です。
本業の収入と合算されるため、副業収入は「知らないうちに税金で損する」リスクが常にあります。
年間20万円を超えれば確定申告が必要になり、たとえそれ未満でも住民税の申告が必要な場合がある――この「申告ルール」を知っておくだけで大きなトラブルは避けられます。
次に、控除や経費は「使えるものは全部使う」のが鉄則です。
控除や経費を漏れなく計上することで、無駄な税金支払いをしっかりカットできます。
「これは経費になるの?」「この控除は使える?」と迷ったら、まず調べて、必要なら税理士や役所の無料相談を活用するのもアリです。
そして、家計管理と副業収入の仕組みづくりも重要です。
副業専用口座を用意し、日々の収入・支出を記録する。
収入の使い道ルールを決め、目的に沿った使い方を意識する――
この繰り返しが、結果的に「副業の手取り最大化」につながります。
私も最初は「難しそう」「面倒くさい」と感じていましたが、実際にやってみると意外とシンプルでした。
最初の一歩さえ踏み出せば、あとは流れ作業です。
副業で大切なのは「コツコツ継続」と「正しい知識で損をしないこと」。
トラブルなく、家族と自分の未来のためにお金を残していきましょう。
これから副業にチャレンジする方も、すでに始めている方も、
「知っているかどうか」だけで手取りに大きな差がつきます。
今日からできる対策を一つずつ始めて、着実に“手取りアップ”を目指してください。